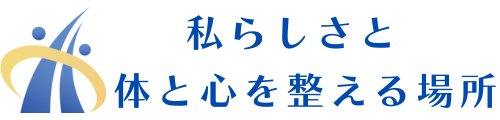歩き方が変わると、世界の見え方が変わる
歩くという動作は、毎日当たり前のように行っています。しかし、その「当たり前」の歩き方を変えるだけで、世界の見え方が変わることをご存知でしょうか?
歩き方が変わると目線が変わり、姿勢が良くなることで自信が生まれます。そうすると、周囲の人の反応も変わり、受け取る情報や感覚も変わります。結果として、心にゆとりが生まれ、ストレスも軽減されるのです。
ほとんどの人は「正しい歩き方」を習ったことがない
私たちは「歩く」ことを自然に身につけましたが、実は多くの人が正しい歩き方を学んだことがありません。なんとなく歩いているうちに、無意識の癖がつき、気づかぬうちに体に負担をかけていることも少なくありません。
例えば、歩き方を変え、靴を変えて正しく歩くようにしたら、筋肉のつき方が変わり、むくみにくくなり、体調が良くなったという人もいます。「歩き方を変えるなんて思いもしなかったけれど、当たり前を見直すことで人生の方向が変わる瞬間がある」と感じることもあるのです。
間違った歩き方が体に与える影響
正しく歩いているつもりでも、実は間違った歩き方をしている人は多いです。その結果、知らず知らずのうちに体に負担をかけ、不調を引き起こしていることがあります。
1. すり足歩行 → むくみやすくなる
すり足で歩くと、足の筋肉が十分に使われません。特にふくらはぎの筋肉が働かず、血液の循環が悪くなるため、むくみや冷えの原因になります。ふくらはぎは「第二の心臓」とも呼ばれ、血液を心臓に戻すポンプの役割を担っています。正しく歩くためには、かかとから着地し、つま先で地面を蹴るように意識することが重要です。
2. 内股歩き → 骨盤の歪みや腰痛の原因に
内股で歩くと、太ももの内側の筋肉ばかり使われ、外側の筋肉が弱くなります。その結果、骨盤の位置がズレやすくなり、腰や膝に負担がかかります。特に女性に多く見られる歩き方ですが、これが慢性化すると、O脚やX脚を引き起こし、股関節の不調につながることもあります。改善するためには、膝を正面に向け、足裏全体をバランスよく使う意識を持つことが大切です。
3. 猫背歩行 → 呼吸が浅くなり疲れやすい
背中を丸めて歩くと、肺が圧迫され、呼吸が浅くなります。その結果、酸素の供給量が減り、疲れやすくなるだけでなく、自律神経のバランスも乱れやすくなります。猫背の原因は、足の使い方だけでなく、普段の姿勢にも影響を受けます。正しく歩くためには、背筋を伸ばし、肩の力を抜いて歩くことを心がけるとよいでしょう。
4. 片足重心歩行 → 体のバランスが崩れやすい
片足に重心をかけて歩くクセがあると、左右の筋力バランスが崩れ、腰や膝に負担がかかります。特に、靴の外側ばかりすり減る人は、この歩き方になっている可能性が高いです。これを改善するには、足裏全体を意識し、均等に体重をかけながら歩くようにすることが大切です。
このように、間違った歩き方は体全体に悪影響を及ぼします。しかし、逆に言えば、歩き方を見直すことでこれらの不調を改善することができるのです。
筋肉が正しく働くことで、体は本来の機能を発揮する
私たちの体は、筋肉が適切に働くことで初めて本来の機能を発揮します。しかし、運動不足や誤った歩き方によって筋肉が使われないと、体の機能が低下し、不調につながります。
「運動不足」とは、単に運動をしないことではなく、「体が本来の働きを発揮できていない状態」でもあるのです。正しい歩き方を身につけることは、日常の中で体を機能的に動かす習慣を作る第一歩になります。
歩き方を変えることは人生を変えること
歩き方を意識するだけで、姿勢が整い、筋肉の使い方が変わり、体の調子が良くなります。さらに、目線が上がり、心にゆとりが生まれ、世界の見え方まで変わるのです。
「自分は正しく歩けている」と思っている人こそ、一度歩き方を見直してみることをおすすめします。今日から、自分の歩き方に意識を向け、より良い人生の一歩を踏み出してみませんか?